.png)
2017.04.26
自由の森学園が電力をみんな電力に切り替えたのは、安くなる価格だけが理由ではなかった。私たちの生活を根底で支え、社会を構築するのに不可欠な電力と共生する在り方が、そこにあっただろうか。 「みんなの電力」ではなく、「みんな電力」。それはつまり、誰かに任せっきりではなく、お互いに顔が見える関係で、一人一人がつくっていく社会のかたち。 全3回の自由の森学園・鬼沢理事長インタビューの第2回を、お届けします。
連載 第1回はこちら https://tadori.jp/articles/440 ーそんな中、みんな電力を選んだ理由は? 鬼沢 僕は経営の会議で、「基準は4つある」と提案しました。 第一は、自然エネルギーの比率。どれほど、再生可能エネルギーを使っているか。 2番目は、経営の安定性。いきなり方針が変わっちゃうとか、潰れちゃうとかは困るから、経営が安定していて、責任をもって電力を供給してくれること。 3番目は価格。「うんと高くてもいい」という議論もなくはないけれど、それは経営合理性からいって困る。できれば安く。ただ、「安かろう、悪かろう」は困るけど。 4番目は、実はここが最終的には「みんな電力」の決め手だったんだけど、この学園の教育との親和性ということを考えました。

木工室。生徒たちは授業の中でも、木材と触れ合い、ベンチや棚などをつくりながら馴染みを深めていく
ーそれはどの部分でしょう? 鬼沢 「顔が見える」ということ。つまり、福島で何が起きていても、顔が見えなければ、どこかの人たちが「自分らの儲けのために原発を誘致して、あんな事故になって自業自得」と思うかもしれない。 そうじゃなくて、「電力を供給してる人たち、その周辺に生きてる人たちは、どんな人たちなの?」ということが、ちゃんとわかる。あの事故については、「そういう繋がりが途切れたから、ああなったんだ」と思うわけです。実際にあそこに自分の親戚が生きていれば、当たり前に親身になれているはずだったと思う。そこにいる人たちに「自分たちと同じ、想いや暮らしがある人間なんだ」って思って電気を使うことは、「とても大事な教育なんじゃないの?」と思ったんですよ。 距離の近い、顔が見える関係で、電力を供給していただき、それを自分たちが大切に使うという感覚は、例えば農産物で言う「地産地消」にも繋がります。そしてエネルギーは、本来ならば地産地消であるべきで。 僕がイメージしたのは、じゃあそれが八王子の酪農家さんから来ている電気だったら、いずれは生徒たちがそういうところに出掛けて行って、電力を供給してくださってる方の話を聞いたり、場面を見たりということが教育活動として展開することが、「みんな電力とだったら可能だ」と。それは、誰かが巨大なメガーソーラーをどこかに持ってて、設置されている誰もいないようなところに行って、「すげえな」と言うのとは違う。 ー血が通ってると言いますか、、 鬼沢 それがやっぱり、みんな電力の強みで。実は価格的には、みんな電力よりも安いところもあった。でも自由の森は教育機関だから、「子どもたちのその後にどういう風にプラスになるか」と考えた時に、大石社長はそこまで引き受けてくれるという話でした。「それならば」ということで、みんな電力にしたんです。

ー授業の一環としてだけでなく、始業式にもエネルギーを使われたと。 鬼沢 普段理事長は生徒の前にあまり出ないんだけど、全校集会で「異例だけど、僕が話をします」と。9月1日、切り替えの日に、僕は生徒に向けて「夏休みが終わって、今日から授業が始まる。でも福島には未だに、自分の学校に行けない子どもたちがいるんだよ」という話からスタートしたの。 やっぱり、あの大きな事故は、僕は、都会の人たちが湯水のようにエネルギーを使ってるという、その中から生まれた部分を感じています。だから、やっぱり「君たちにはエネルギーを大事に使って欲しい」、「節電しろ」ということを前段で喋って(笑)、ついては「電力をみんな電力に替える」、「今日は社長も来てくださっている」と。 ーまさに顔が見える状態からのスタート。 鬼沢 それでその日の午後、関心のある子たちは集まって、大石社長の話を聞いてくれた。そこで大石さんのお話は、まず「コンセントの向こう側を想像できますか?」というところからスタートしたんだよね。
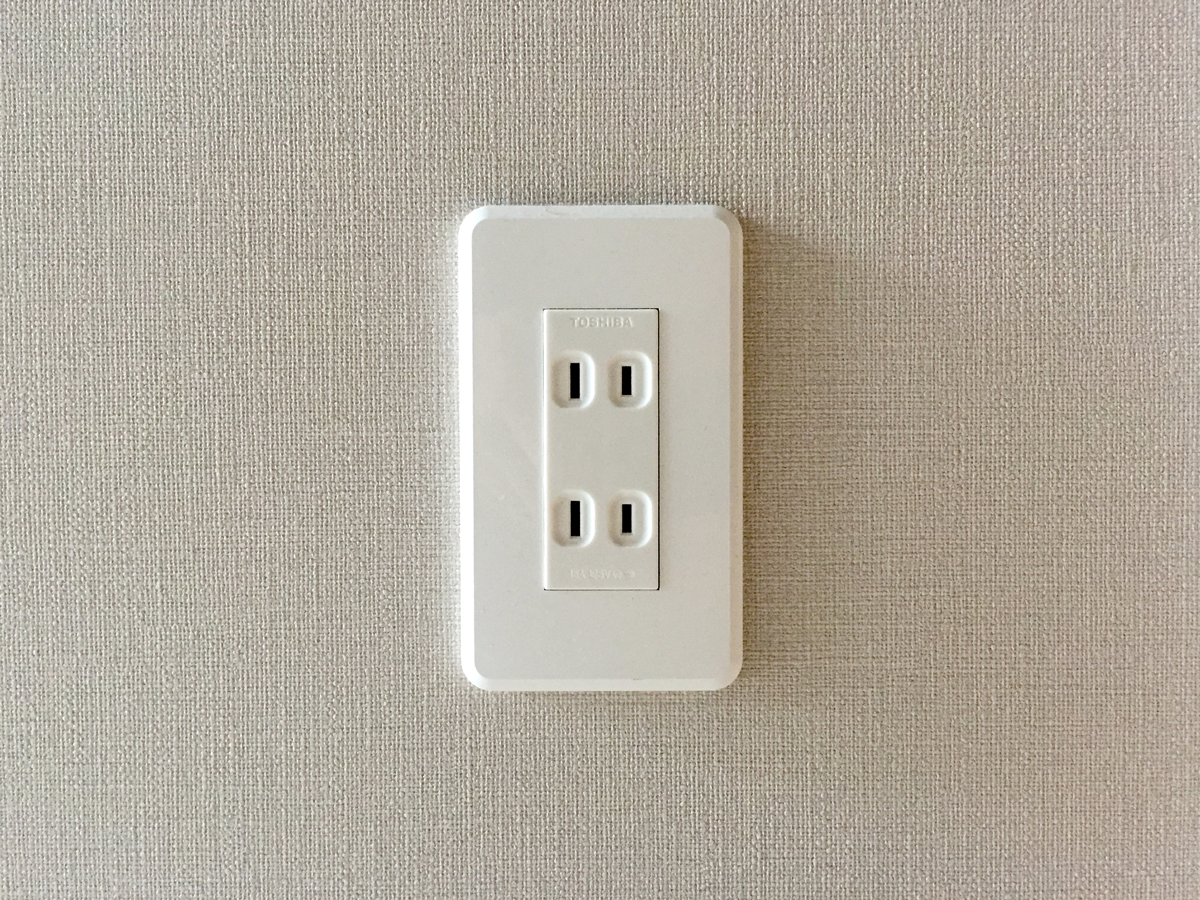
日々当たり前に挿したコンセントの先で、どんな人がどんな風に発電しているかを想像してみる
ー生徒たちからの反応はありますか? 鬼沢 大石社長は、石油は現在紛争の舞台となっている中東から来ていることはもちろん、ウラン鉱山で働く労働者のことにまで言及した。ある程度わかっている子もいるし、そもそもの構造をどう変えていけるかと考える子もいる。あとは「環境学」という講座が社会科として新しく生まれて、それは僕の林業とはまた別で、環境系の様々な分野を扱うんだけど、この前も人を集めてイベントをやったりしていました。 ー電力に関する取り組みで、今まで特に大きな弊害などもなかった? 鬼沢 「なんでそんなわけのわからないことやってるの?」と言われたことは、今のところないです。 ー実際、個性豊かな面々を排出されています。最近ですと星野源さん、浜野謙太(ハマケン)さんなど、ユニークな方々が活躍される背景には、少なからず教育方針の影響があるでしょうか? 鬼沢 だと思うけどね。 源ちゃんは、中一から高三まで僕の学年にいたけど、あんなになるなんて誰も思ってないよ。大人しい、普通の子。同学年にずっとやんちゃな子はたくさんいた。まあ、ユージはえらくやんちゃだったよね。ハマケンも在学中からあんな感じだった。

美術棟写真
ーそれぞれ、共通している「イズム」をお持ちで学園に呼応して来るのか、ここに来て花開くのか。 鬼沢 両方だと思うんだけど、この学校は成績のいい悪い、スポーツできるできないという、俗に言う学校のヒエラルキーとは違うんですよ。 ーそのヒエラルキーとは? 鬼沢 子どもたちにとっては、「やりたいことが見つかったかどうか」が重要なんです。既存のものじゃない価値尺度で生きるには、「何者かでなければならない」という辛さはあるわけ。その中で例えば「スポーツができるようになった」、「ギターが上手い」とか、歌やダンス、とにかく何らかのかたちで、一生貫いていける何かに出会うかどうか。いいも悪いも、そこを彼らはずっと問われている。 僕には「そんなに無理して、自分探しすんなよ」という想いもあるんです。「そんな上手くいくわけねえじゃん」と思うんですが、でもやっぱりここでは、それぞれの「個性的であらねばならぬ」という何かが働いちゃって、ちょっとしんどそう。 それはキツいでしょう?別に人と一緒だって、いい部分もあるじゃん。だけどなんとなく、自由の森に流れてる空気には「人と違わねばならない」というある種のバイアスがあると思う。そのさじ加減がどの程度かっていうのが重要で、やっぱり「みんな同じにしろ」というのはいけない。その雰囲気の中で子どもたちは6年とか3年とかを生きて、何かを見つけて、もしくは探索中のまま、出て行く。

理事長の案内で校内を歩いていると、先生の監督のもと、生徒たちが木を切り倒す場面に出くわした
ーある意味で、教育界におけるカウンターとしての自由の森、、! 鬼沢 そう。オルタナティブを目指してきました。 そして今、僕らが言い始めているのは「持続可能性」、「サステナブル」ということ。この学校ができたのは85年なんだけど、その価値は当時、つまりバブルの時代から比べると、遥かにウェイトが大きくなっている。今の世界を見ていくキーワードの一つは、「持続可能であるのか?」ということで、それは原発だけの問題じゃないし、温暖化の問題もあって。 ーそこのメッセージは学生に響いていますか? 鬼沢 この学校に入る前から、家庭環境の中でこういうことをかなり重視して生きてきた子たちも多くて、すぐストーンと入る子もいるし、全然ピンとこない子もいる。でもおそらく、親全体をトータルを見れば、比較的そういうことに意識を持っている人たちが多いんじゃないかな。

無事、倒木完了。迫力ある場面でした
連載 第1回はこちら https://tadori.jp/articles/440

エネルギーのポータルサイト「ENECT」編集長。1975年東京生、School of Visual Arts卒。96〜01年NY在住、2012〜15年福島市在住。家事と生活の現場から見えるSDGs実践家。あらゆる生命を軸に社会を促す「BIOCRACY(ビオクラシー)」提唱。著書に『虚人と巨人』(辰巳出版)など https://www.facebook.com/dojo.screening X @soilscreening
あなたの気になるモノゴト、タドリストがタドって
記事にします。リクエストをお待ちしております!